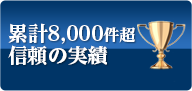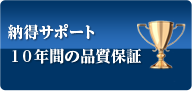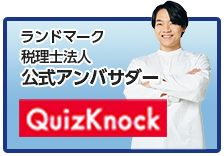義務となる相続税申告
相続税はどのような場合に申告するべきなのでしょうか。
相続が発生し、財産を受け取った時、申告が必要な場合と必要でない場合があります。
申告が必要な場合は、遺産総額が基礎控除を超える時で、必要でない場合は、遺産総額が基礎控除を超えない時です。
| 申告必要 | 遺産総額 > 基礎控除 |
| 申告不要 | 遺産総額 < 基礎控除 |
遺産総額とは、被相続人の相続財産で金銭的価値に換算できるものすべての合計額になります。不動産、現預金、株、借入金等が該当します。
基礎控除は、「3,000万+600万×法定相続人の数」で求めることができます。法定相続人とは民法で認められている一定の相続人のことをいいます。例えば、父が亡くなり、母、長男、長女がいる場合、法定相続人は3人となります。基礎控除の式に当てはめると、3,000万+600万×3人=4,800万となり、基礎控除は4,800万となります。
遺産総額では、特例を適用して減らすことも可能です。しかし、その時に申告が不要になるか否かは特例によって変わってくるため、そのことも含めて、申告が必要な時と不要な時について、さらに詳しく解説していきます。
特例の一つに小規模宅地等の特例というものがあります。この小規模宅地等の特例を使用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなった場合でも、申告義務は不要にはなりません。つまり、小規模宅地等の特例で遺産総額が基礎控除よりも少なくなったとしても申告は必要となります。なぜなら、小規模宅地等の特例を適用するには申告が必要だからです。
例えば、法定相続人が3人で、相続財産が自宅の土地6,000万円、預金が2,000万円だと仮定します。基礎控除は、3,000万+600万×3人=4,800万となります。遺産総額は6,000万+2,000万=8,000万となり、基礎控除よりも多くなるため、申告は必要となります。
ここで、小規模宅地等の特例を適用(要件をすべて満たしていることが前提)すると、自宅の土地の評価額が80%減されるため、6,000万円→1,200万円となります。そこで、遺産総額が1,200万+2,000万=3,200万となり、基礎控除よりも少なくなるため、申告は必要ないと考えてはいけません。小規模宅地等の特例を適用するには、そもそも申告が必要になるため、申告義務がなくなることはありません。
他にも、配偶者の税額軽減という制度もありますが、小規模宅地等の特例と同様に、申告が必要な特例のため、適用することで遺産総額が基礎控除を下回っても、申告義務がなくなることはありません。
では、申告が不要な時はどういう場合でしょうか。
一つは、障害者控除、相次相続控除等を適用して、相続税が発生しない場合です。これらの特例は小規模宅地等の特例と違い、申告が不要のため、納税の申告義務も不要ということです。
以上に挙げた債務は支払証書やレシート、領収書をもとに計算します。これらは相続税の計算に必要な資料として日付や支払先がハッキリ分かる形で原本を保管しておくことが大切です。
さらに生命保険、退職金には非課税枠というものがあり、それを適用することで遺産総額が基礎控除を下回る場合には申告義務はありません。
その他にもそれぞれの状況によって申告が必要なケースや申告が必要でないケースがあります。上記の例だけでは、判断できない場合には一度専門家である税理士に相談すると良いでしょう。
 『相続税申告』に関する関連情報
『相続税申告』に関する関連情報
- 債務がある場合
- 相続税申告の報酬
- 義務となる相続税申告
- 相続税の申告の原本還付
- 成年後見人を立てる場合
- 未分割での申告
- 特別代理人を立てる
- 相続税申告と遺産分割協議書
- ペナルティ
- 相続税申告における書面添付
- 相続時精算課税
- 税務署からお尋ねがあった場合
- 申告に漏れがある場合
- 修正申告
- 提出期限の延長
- 更正の請求
- 申告時のマイナンバーの要否
- 遺言執行者の選任
- 遺言書と相続税申告
- 遺贈があった場合
- 提出する添付書類
- 必要な書類
- 申告の期限
- 自分で行う場合
- 申告をしない
- 申告が必要となるケース
- 申告が不要な場合
- 税理士に依頼する
- 残高証明
- 印鑑証明
- 延滞
- 延納
- 物納
- 基礎控除以下の場合
- 申告における戸籍謄本
- 退職金
- 認知症の方がいる場合
- 不動産登記
- 未成年の場合
- 相続税申告における現金
- 代理人の場合
- 代償金
- 代償分割
- 申告前に相続人死亡となった場合
- 調査
- 無申告の場合
- 相続税申告に必要な添付書類一覧
- 数次相続がある場合の相続手続きの進め方
- 相続税の申告書にマイナンバーを記載する必要性と提出時の注意点
- 相続税申告の報酬相場・料金と失敗しない税理士選びのポイント
- 【相続税申告書の書き方】第9表から書き始めることを推奨する理由
- 相続税の申告は自分でできる!準備から提出までの6ステップを全解説
- 相続手続きがラクになる~法定相続情報証明制度のメリットと利用方法~
- 相続財産になるものは?課税対象となる財産には何があるか解説!
- 相続人の範囲はどこからどこ?様々な相続パターンも紹介!
- 相続税対策に養子縁組を行うメリットとデメリットを解説
- 家の相続をするために知っておきたい手続きの流れや相続税の仕組み
- 家を相続したときの税金は?具体的な節税対策も解説!
- 生前贈与の手続きと贈与契約書
- 相続した不動産を売却するときの税金は?特例や注意点も解説!
- 名義預金を見つけた場合の対策とは?
- 異母兄弟に相続権はある?相続割合やトラブルについて解説!
- 相続税申告後に新たな財産が!修正申告に必要な手続きと注意点を解説!
- 基礎控除はいくら?相続税が発生する基準や申告すべき理由を解説
- 相続税の無料相談はどこでできる?4つの相談先を解説!
- 一人っ子相続のメリット・デメリットと、手続きや相続税対策について知っておくべきことを解説
- 相続税で延滞税がかかってしまう状況やそのほかの相続税のペナルティについて解説
- 不動産取得税とは?相続時に課税されるケースや計算方法などを解説
- 相続財産から指し引ける相続費用は?申告方法も解説!
- 書面添付制度とは?記載内容やメリットについて解説
- 死因贈与とは?メリット・デメリットを遺贈や生前贈与と比較しながら解説
- 国際相続では日本の相続税はどうなる? 日本の相続税がかかるパターンと手続きについて解説
- 相続税の手続きの流れは?期限や手順について解説!
- 払いすぎた相続税の還付を受ける「相続税の更正の請求」について知っておきたいことと手続きについて解説
- 住宅取得資金贈与の特例とは? 制度内容や申請方法について解説
- 山林を相続したとき、相続税はどうなる? 山林の相続税評価方法を解説
- NISA口座を相続すると、税金はかかる?
- 遺産を相続すると相続税がかかる?課税条件や計算方法、お得な控除制度を解説
- 相続財産を寄付するとどんなメリットがある? 寄付したときの税金のルールや節税効果について解説
- 遺言書がある場合の相続税への影響は?申告方法や生前対策を徹底解説
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】