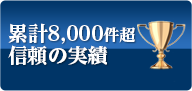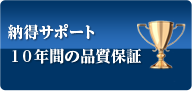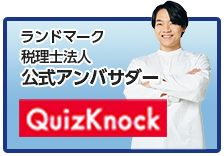相続税の配偶者控除と修正申告
ここでは、相続税の配偶者控除と修正申告の関係についてご案内させていただきます。
修正申告とは、一般に既に申告・納税を済ませた税について、その後誤りの発見又は特別の状況の発生により初めの納税額が不足していたことが判明した場合に改めて申告を行うことを言います。このように、通常は納める税金が増加する場合に行うものですが、配偶者控除に関連しては、納税額が増加しないときにも修正申告を行うことが認められる場合があります。次項以下でご説明します。
相続税の修正申告が必要な場合
相続税は他の税と比較して、申告期限後に生じた事情により税額計算の基礎となる事実関係が変動して納税の額が増減することが多い税目であると言えます。相続税法では修正申告の特則を設けて、特定の事由が生じたことにより既に確定した相続税額が不足となった場合には、修正申告書を提出することができると定めています。
その事由の主なものとしては、
①遺産分割が行われたことにより課税価格が変動したこと
②認知や推定相続人の廃除に関する裁判の確定等により相続人が異動したこと
③遺贈に関する遺言書が発見されたこと
等があります。このうち特に①の遺産分割が行われたことによる変動は、配偶者控除の適用に直接的な影響を及ぼすことが多いであろうと考えられます。
配偶者控除と修正申告
配偶者控除の適用を受けるには、既に説明したとおり、申告期限までに遺産分割が行われて配偶者の実際の取得財産が確定し、それに基づいて相続税申告書の提出を行うことが要件とされています。しかし申告期限までに遺産分割ができない場合には、配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行い、その後遺産分割が行われた後に更正の請求又は修正申告を行うことで、配偶者控除の適用を受けることになります。
更正の請求は既に確定した税額が過大であって還付を受けることになる場合に行うことができ、逆に既に確定した税額が過少であった場合には修正申告を行って不足の税額を納めることになります。
このように、修正申告書は納税額の増加が生じるときに限って提出できるものですが、相続税の配偶者控除に関しては、それが申告を要件として認められるものであるため、修正申告により納める税額がない場合にあっても、納付税額ゼロの申告書の提出ができるものとして取扱われています。すなわち配偶者控除の適用を受けて納付すべき相続税額がない申告書を既に提出した者が、その後の分割等によりさらに財産を取得した場合であって、この控除の適用を受ければなお納付すべき相続税額が生じないが、この控除の適用がないとした場合に算出される相続税額が前に提出した申告書の税額を超えることとなるときは、その者は修正申告書の提出をすることができるものとされています。
相続税の修正申告には、通常の相続税申告にも増して難しい判断や手続が必要になります。知識・経験が豊富な相続税専門の税理士事務所を利用することをお勧めします。
 『相続税の配偶者控除』に関する関連情報
『相続税の配偶者控除』に関する関連情報
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】