
親が加入している生命保険の受取人が自分になっていた場合、「親が亡くなって相続が発生した際、生命保険にも税金がかかるのか?」と悩むことも珍しくありません。
生命保険の内容によって相続税・贈与税や所得税がかかるものもあれば、非課税のものもあります。
本記事では、生命保険をはじめとする保険の受取金にかかる税金について解説します。
1 保険金などを受け取ったとき、税金はかかる?
保険金は、種類と契約形態によって税金がかかるものと非課税のものがあります。
非課税になる保険金は、以下のようなものが挙げられます。
- 入院給付金
- 疾病(災害)療養給付金
- がん診断給付金
- 高度障害保険金
- 就業不能保険金
また、事故が原因で支払われる損害保険金も非課税となります。
一方で、保険金に税金がかかるケースは以下のとおりです。
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 個人年金
それぞれの保険金にかかる税金の種類や額については次の項で詳しく解説します。
税金の種類や額は被保険者、保険料負担及び受取人との関係によって異なりますので、
もし、保険金を受け取ったらどのような税金がかかるのか?把握しておくことは大切です。
1-1 生命保険の相続税非課税限度額とは?
生命保険は、被保険者の、死亡・病気・障害といった事態に陥ったとき、家族が経済的に困らないように備える保険です。
そのため、一定の相続税非課税枠が設けられています。
非課税枠は、「500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額」の計算式で求められます。
法定相続人とは、死亡した被保険者の配偶者、子ども、親(子どもがいない場合)、祖父母、兄弟姉妹(子ども、親がいない場合)などです。
子どもなど法定相続人の数が多いほど、非課税限度額が増えていきます。
例えば、配偶者だけならば非課税限度枠は500万円ですが、配偶者と子どもが3人いるなら、2000万円まで非課税限度枠が広がります。
なお、相続放棄をした人数も法定相続人に含めます。
生命保険をかけている方が亡くなった場合は、法定相続人が何人いるか調査する必要があります。
2【パターン別】死亡保険金を受取る際にかかる税金
死亡保険金を受け取る際にかかる税金は、契約者と受取人の関係によって異なります。
生命保険を契約した際の「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の3者によって、相続税・贈与税・所得税の課税対象となります。
契約者とは、保険を契約した人を、被保険者とは保険がかけられている人のことを指し、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
保険金受取人は保険金を受け取る人のことを指します。
生命保険の場合、契約者が保険料負担者であったとすると、保険金受取人が契約者(=保険料負担者)と同じか、異なるかによってそれぞれ保険金にかかる税金が変わってきます。
次の項目からパターン別にどのような場合に、何の税金がかかるのか確認していきましょう。
2-1 契約者と受取人が同じ
契約者と受取人が同じ場合は、所得税と住民税がかかります。
所得税は、所得を得た際に発生する税金です。
契約者と受取人が同じなので、相続や贈与ではなく受取人の一時所得になるという考え方です。
例えば、夫が妻に保険金をかけて受取人を夫自身にしている場合などが該当します。
2-2 契約者と受取人が異なる
契約者と受取人が異なる場合、相続税が発生します。
例えば契約者と被保険者が夫で妻や子供が受取人になった場合です。
また、受取人が孫(代襲相続の場合を除く)だった場合も相続税は発生します。
相続税が2割加算されるので注意が必要です。
2-3 契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税が発生します。
例えば、契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子どもの場合などが該当します。
この場合は、生きている妻から子どもが生命保険金を受け取るので、相続税ではなく贈与税となります。
3【パターン別】満期保険金を受取る際にかかる税金
ここでは、満期保険金を受け取る際にかかる税金を紹介します。
死亡保険とは異なり、満期保険金は被保険者が生きている場合に支払われます。
かかる税金も死亡保険金とは異なるので、確認しておきましょう。
3-1 契約者と受取人が同じ
契約者と満期保険金の受取人が同じ場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
また、満期保険金が「金融類似商品」に該当する場合は源泉分離課税になります。
- 5年以内に満期となる「一時払養老保険」などの商品(契約日から5年以内に保険を解約した場合)
源泉分離課税は、配当金を含む満期保険金から、払い込み保険料を差し引いた差額に対して課せられます。
税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を併せて20.315%です。
源泉分離課税の場合は、保険会社が源泉徴収を行ったうえで受取人に振り込みます。
そのため、受取人が確定申告する必要はありません。
一方、一時所得として課税対象となる所得税の場合は、以下のような場合を除いて確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円以下であり、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円(一時所得含む)以下の場合
- 公的年金の収入が400万円以下であり、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円(一時所得含む)以下の場合
- 2か所以上から給与の支払いを受ける場合
これは、所得が20万円以下の場合は確定申告が不要というルールに基づいた決まりです。
控除できる所得がある可能性もあるので、できるならば確定申告を行いましょう。
ただし、確定申告を行う場合は一時所得も申告する必要があるので注意が必要です。
近年はオンラインで提出できます。
3-2 契約者と受取人が異なる
契約者と受取人が異なる場合、贈与税が発生します。
保険金も贈与とみなされるためです。
なお、契約者が親で子どもが受取人にすると親が60歳以上、子どもが18歳以上ならば「相続時精算課税制度」が利用できます。
この制度を利用すると、2,500万円の特別控除を適用できるので、金額によっては贈与税がかかりませんが、親が死亡した際には、相続財産に加算しなければなりません。
3-3 満期保険金と解約返戻金の違いとは?
満期保険金とは、保険期間が満了したときに受け取れる保険金の総称です。
例えば、養老保険は満期まで生存していた場合にまとまった額のお金が払われるので、「満期保険金扱い」となります。
解約返戻金とは、保険を途中で解約した際に戻ってくるお金です。
解約返戻金が発生する保険には、「終身保険」があります。
終身保険とは、死亡保障や高度障害保障が生涯続くタイプの生命保険です。
満了がないため、契約期間中に解約すると「解約返戻金」となります。
契約から一定数を超えると払い込んだ保険料より解約払戻金のほうが多くなるため、貯蓄代わりとしても利用される保険です。
かかる税金も保険金の支払われ方によって異なる場合があるので、自身が加入している保険に満期があるのか終身なのか確かめておきましょう。
また、子どもが成人している場合は一度親がかけている保険について説明しておくといざというときに安心です。
4【パターン別】個人年金保険の年金を受け取ったときの税金
ここでは、個人年金保険から年金を受け取った場合に発生する税金について解説します。
被保険者が生存している場合と死亡している場合ではかかる税金が異なる場合があるので、確認が必要です。
4-1 被保険者が生存している場合
被保険者が現存している場合、年金を受け取るたびに所得税が発生します。
また、受取人が契約者と同じ場合と異なる場合では課せられる税金が異なるので注意が必要です。
4-1-1 契約者と受取人が同じ
契約者と受取人が同じ場合は、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)がかかります。
契約者と受取人が同じならば、被保険者が異なってもかまいません。
例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合は契約者と受取人が同じと判断されます。
なお、課税されるのは受取人です。
4-1-2 契約者と受取人が異なる
契約者と受取人が異なる場合は、年金を受給が開始された際に年金の権利評価額に贈与税がかかります。
それに加えて、年金を受け取るたびに所得税(雑所得)がかかります。
契約者と受取人が異なる場合とは、夫が妻に個人年金をかけて、受取人に妻を指定した場合などです。
所得税に加えて贈与税もかかるので、額によっては受け取れる年金の額が減ってしまいます。
したがって、個人年金をかける場合は、契約者と受取人を一緒にした贈与税がかからない分お得です。
4-2 年金受取開始後、被保険者が死亡した場合(確定年金・保証期間付年金)
個人年金は種類によって被保険者が死亡すると年金の受給が止まる商品と、被保険者が生きている限り年金が受給できる商品があります。
一例を挙げると国定年金は、決められた期間保険金が支払われるタイプの保険です。
契約時に定めた期間は、被保険者の生死にかかわらず年金の受取人に保険が支払われます。
また、保証期間付有期年金タイプの個人年金保険の場合は、年金受取期間かつ保証期間終了後に被保険者が亡くなると年金の受給が終了します。
被保険者が死亡した後受取人にどのくらいの期間年金が受け取れるか、被保険者が元気のうちに確認しておくのがおすすめです。
また、必要ならば年金の受け取り期間を変更するなどの対処が必要です。
4-2-1 契約者、被保険者、年金受取人が同じ
個人年金の契約者、被保険者、年金受取人が同じ場合は、一括受け取りを選択した場合に相続税がかかります。
その一方で所得税はかかりません。
年金形式で受給すると、被保険者が亡くなった後に受ける年金の権利評価額に対し、相続税がかかります。
さらに、年金を受け取るたびに所得税(雑所得)がかかります。
契約者・被保険者・年金受取人が同一人の場合とは、夫が自分自身に年金をかけて受取人を自分にしていたが、受取の期間を残して死亡し、妻が残りの年金を受け取るケースなどです。
年金の種類によっては、一定期間受取人以外でも年金を受け取れる場合があります。
この場合は、一括で受け取ったほうが金額によっては税金が少ない可能性があります。
4-2-2 契約者、被保険者が同じで、年金受取人が異なる
契約者、被保険者が同じで、年金受取人が異なる場合、年金の受給時にすでに贈与税の対象となっています。
そのため、一括でも年金の形で受け取る場合でも、かかる税金は「所得税」です。
ただし、一括で受け取った場合は「一時所得」、年金で受け取った場合は「雑所得」で所得税がかかります。
契約者、被保険者が同じで、年金受取人が異なる場合とは、夫が妻に保険金をかけて受取人が妻の場合です。
家族まとめて保険に入ったなどの理由で契約者と被保険者が同じ、年金受取人が異なるといった場合もあるでしょう。
4-2-3 契約者、年金受取人が同じで、被保険者が異なる
契約者、年金受取人が同じで、被保険者が異なる場合は、所得税のみが発生します。
贈与税は発生しません。
できるだけ税金を発生させずに長く個人年金を受け取りたい場合は、契約者、年金受取人が同じで、被保険者が異なる形で契約する方法もあります。
所得税の額は受給する金額によって異なります。
受け取る金額が多いほど雑所得は多くなるので、注意が必要です。
4-2-4 被保険者、年金受取人が同じで、契約者が異なる
被保険者、年金受取人が同じで、契約者が異なる場合は、かかる税金は所得税と贈与税です。
未払いの年金を契約者が一括して受け取る場合は、未払いの年金現価に対して所得税がかかります。
また、事情があって年金受取人以外の方が未払いの年金を一括して受け取った場合は年金現価に対して贈与税と所得税がかかります。
例えば、年金受取人が高齢で寝たきりになっており、財産管理のために受取人の子どもが一括払いされた未払いの年金を受け取りたい場合などです。
年金の形で分割して受け取る場合も同様です。
年金の受取人以外の方が年金を受給する場合は所得税とは別に贈与税が発生します。
5 まとめ
本記事では、生命保険に対して発生する税金について解説しました。
被保険者が死亡し、保険金を受け取った場合は必ず相続税・贈与税・所得税のどれかが発生します。
ただし、相続税や贈与税はいろいろな優遇制度や減税制度があるため、「せっかく残された家族が経済的に困窮しないようにお金をかけたのに、税金でほとんど持っていかれてしまった」といったことにはなりません。
仮に生前対策を行う際は、親が生命保険に入っているのかどうかだけでも把握するのはとても重要です。
ご自身やご家族の生前対策、生命保険関係の税金など、ご不明な点がございましたら、ぜひランドマーク税理士法人にご相談ください。




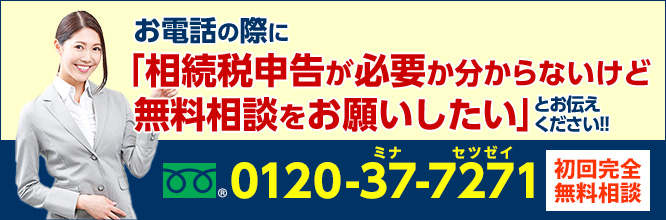
 なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。 無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。



















