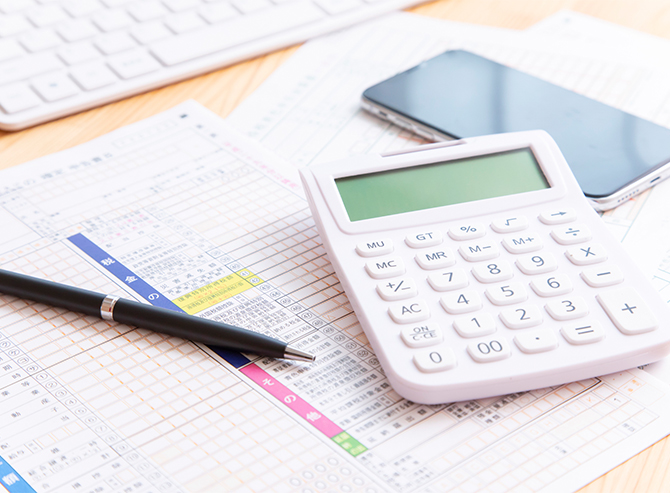
所得税を計算するうえで重要なのが「所得控除」と「税額控除」です。これらの制度を正しく理解し活用することで、納める税金を大きく減らすことができます。
しかし、それぞれの控除には適用条件や手続きがあり、内容も多岐にわたるため、分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、所得控除の主な種類と、控除を受けるための手続き、さらに税額控除についても分かりやすく解説します。
賢く節税するための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
1. 控除とは
「控除」とは、税金を計算する際に、一定の金額を差し引くことで課税対象を少なくする仕組みです。控除には大きく分けて「所得控除」と「税額控除」があり、それぞれ役割が異なります。
所得控除は課税される所得金額を減らすのに対し、税額控除は計算された税額そのものを直接減らす効果があります。
控除を正しく理解し、適切に申告することで、無駄な税負担を避けることができます。
1-1. 所得控除
所得控除は、所得税の課税対象となる「課税所得」を減らすための制度です。
たとえば、医療費控除や社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除などがあり、個人の生活状況や支出に応じて適用されます。控除額が大きいほど課税所得が減り、結果として所得税も軽減されます。
多くの所得控除は年末調整や確定申告で申告が必要です。
1-2. 税額控除
税額控除は、所得控除によって算出された税額から、さらに一定額を直接差し引く制度です。
代表的なものに「住宅ローン控除」や「配当控除」、「外国税額控除」などがあります。
税額控除は、控除額がそのまま納税額に反映されるため、所得控除以上に節税効果が高い場合もあります。
適用には証明書類の提出や確定申告が必要になるケースが多いため、事前に準備をしておきましょう。
2. 所得控除の種類
所得控除には、納税者の生活状況や支出に応じて様々な種類があります。これらを適切に活用することで、課税所得を減らし、税負担を軽減できます。以下で代表的な15の控除について解説します。
2-1. 雑損控除
地震・火災・台風などの自然災害や、盗難・横領によって住宅や家財などの資産に損害を受けた場合に適用される控除です。控除額は、損害額から一定の金額を差し引いた残りを、所得から控除できます。確定申告が必要で、領収書や証明書の添付が求められます。
2-2. 医療費控除
自分や家族のために支払った医療費が年間10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)を超える場合、その超過分が控除されます。通院の交通費や市販薬、歯科治療なども対象に含まれます。明細書の提出と医療費の記録が必要で、確定申告が必須です。
2-3. 社会保険料控除
健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、介護保険料など、法律で定められた社会保険料を支払った場合、その全額が所得控除の対象となります。本人だけでなく、生計を一にする家族の分を支払った場合も含まれます。
2-4. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済、確定拠出年金(iDeCo)などの掛金は、全額が所得控除の対象となります。個人事業主やフリーランス、自営業者、会社員でも対象制度に加入していれば適用可能です。掛金の支払いを証明する書類の提出が必要です。
2-5. 生命保険料控除
生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合、一定の上限内で所得控除が受けられます。旧制度と新制度で控除限度額が異なり、最大で年間12万円の控除が可能です。保険会社から送付される証明書が必要です。
2-6. 地震保険料控除
地震保険や旧長期損害保険の保険料を支払った場合、最大5万円までの所得控除を受けられます。火災保険単体では対象外です。保険料控除証明書を年末調整または確定申告で提出することで適用されます。
2-7. 寄附金控除
国や地方公共団体、認定NPO法人などへ寄附した場合に適用される控除です。ふるさと納税もこの対象です。2,000円を超える部分が控除され、限度額内で所得控除か税額控除が選べるケースもあります。領収書や受領証明書の提出が必要です。
2-8. 障害者控除
納税者本人、または扶養親族が障害者の場合に受けられる控除です。一般障害者は27万円、特別障害者は40万円が所得から控除されます。同居特別障害者の控除額は75万円です。特別障害者には重度の障害や常時介護が必要な方が該当します。証明書が求められる場合があります。
2-9. 寡婦控除
夫と死別または離婚し、一定の要件を満たす女性が対象です。所得控除は27万円です。扶養親族がいる場合や、合計所得金額が500万円以下であることなどの条件があります。なお、2020年からは「ひとり親控除」との統合も始まっています。
2-10. ひとり親控除
配偶者と死別・離婚した後、子どもなどを扶養しているひとり親が対象です。合計所得金額が500万円以下で、扶養親族が1人以上いる場合、35万円の所得控除を受けられます。性別を問わず適用されるのが特徴です。
2-11. 勤労学生控除
学生でありながら一定の収入がある人に対する控除です。合計所得が75万円以下(給与所得のみの場合は130万円以下)で、勤労による所得がある学生に対して27万円の所得控除が適用されます。学業と就労の両立を支援する制度です。
2-12. 配偶者控除
納税者に扶養する配偶者(合計所得48万円以下)がいる場合に適用されます。納税者の合計所得金額が1000万円以下であれば最大38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)の控除が受けられます。年末調整または確定申告で申告が必要です。
2-13. 配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超えた場合でも、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下で配偶者の合計所得が133万円以下であれば段階的に控除が受けられます。納税者の合計所得が900万円以下であれば、最大38万円の控除となります。共働き世帯にも適用されやすい制度です。
2-14. 扶養控除
子どもや高齢の親など、生計を一にする扶養親族がいる場合に適用されます。年齢により控除額が異なり、16歳以上で38万円、19?22歳の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円などが控除されます。
2-15. 基礎控除
すべての納税者に一律で適用される控除です。合計所得が2,400万円以下であれば、48万円の控除が受けられます。所得が増えると段階的に控除額が減り、2,500万円を超えると対象外になります。年末調整や確定申告で自動的に適用されます。
3. 控除を受けるために必要な手続きは?
控除を受けるには、正しい手続きを行う必要があります。控除の種類や納税者の立場によって、申告方法や提出書類が異なります。
以下で、給与所得者・個人事業主・確定申告が必要なケースに分けて解説します。
3-1. 給与所得者の場合
給与所得者(会社員やアルバイトなど)は、勤務先で行われる「年末調整」によって多くの所得控除が自動的に適用されます。
年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された税金を年末に精算し、過不足を調整する仕組みです。従業員は年末に「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」などの書類を会社に提出し、配偶者の所得や扶養家族の状況、支払った保険料や共済掛金の情報を記入します。
また、保険会社から送付される控除証明書も添付が必要です。
ただし、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除の初年度、災害損失に関する雑損控除などは年末調整では対応できません。ワンストップ特例を適用してふるさと納税を行った方が確定申告をする場合は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告する必要があります。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
3-2. 個人事業主の場合
個人事業主やフリーランスは、年末調整の仕組みがないため、すべての所得控除や税額控除を自ら確定申告で申請します。
所得税を正しく計算するには、1年間の売上や経費、各種支出を正確に帳簿へ記録し、必要に応じて領収書や証明書を保存しておくことが基本です。医療費控除や生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除なども、すべて確定申告で申請します。
特に青色申告を選択している場合は、複式簿記による帳簿の作成や貸借対照表・損益計算書などの提出が求められます。
これにより、最大65万円の青色申告特別控除も受けられます。申告期間は例年2月16日から3月15日までで、この期間内に税務署へ申告書を提出する必要があります。
期限を過ぎると控除が受けられなくなる可能性もあるため、早めの準備が大切です。
3-3. 確定申告が必要なケース
会社員などの給与所得者でも、すべての控除が年末調整で完結するわけではありません。以下のような場合は、翌年の確定申告が必要です。
- 医療費控除を受けたい場合
- ふるさと納税をワンストップ特例で申請しなかった場合(寄附金控除)
- 住宅ローン控除を初めて受ける年
- 自然災害や盗難などで損害を受けた場合(雑損控除)
- 副業や不動産収入など、給与以外の所得が20万円を超える場合。
また、源泉徴収が行われていない株式の譲渡益、仮想通貨の売却益などがある場合も、申告が必要です。これらを申告せずに放置すると、控除が受けられないだけでなく、後から税務署に指摘され、延滞税や加算税を課される可能性もあります。
所得控除や税額控除を適切に受けるためにも、自分が該当するかどうかを早めに確認しておきましょう。
4. 主な税額控除
税額控除とは、所得控除と異なり、計算された所得税額から直接一定額を差し引く仕組みで、納税額を大きく減らせるのが特徴です。代表的なものに「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」があり、マイホームの取得やリフォームのための借入金に応じて一定額が控除されます。
そのほか、株式の配当所得に対して二重課税を調整する「配当控除」、外国で納税した場合の「外国税額控除」、政党や政治資金団体への寄附に適用される「政党等寄附金特別控除」などもあります。
これらの控除を受けるには、多くの場合で確定申告が必要となり、控除対象となる証明書類や明細書の提出も求められます。
制度ごとに適用条件や控除額の上限が異なるため、事前に確認し、正確に手続きすることが重要です。
5.まとめ
税金の負担を軽くするには、所得控除や税額控除の制度を正しく理解し、自分に該当する控除を見極めることが重要です。
多くの控除は年末調整で適用されますが、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など、確定申告が必要なケースもあります。
控除には申告期限や必要書類があり、準備不足によって適用を逃す可能性もあるため、早めに確認しておくことが大切です。特に副業収入や資産運用などがある方は、年末調整だけでは不十分なこともあるため注意が必要です。
控除を正しく活用すれば、納税額を抑えられるだけでなく、将来に向けた資金の確保にもつながります。税金についての知識を深め、賢く制度を使いこなして、家計の健全化を目指しましょう。




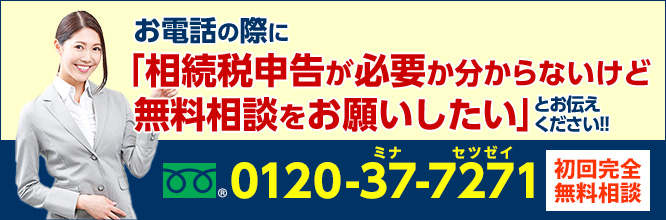
 なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。 無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。



















